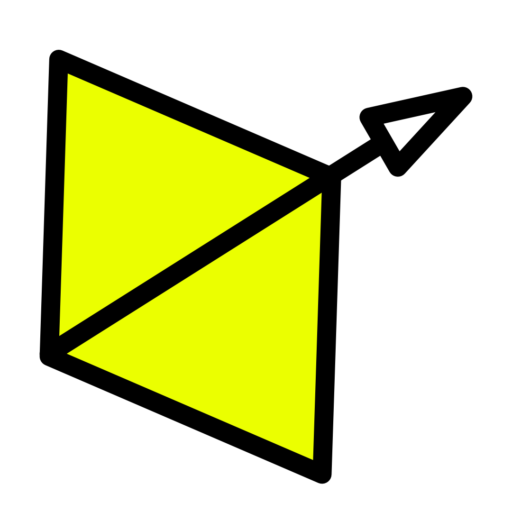「このデータで何かできない?」の落とし穴
少し古い話ですが2010年代に、「AIが大量のデータを解析し、人間の発想を超えたインサイトを導き出す」というメッセージをよく耳にしたのではないでしょうか。
これはITベンダーやコンサル、メディア、政府や自治体、さまざまな企業が語ってきたメッセージです。一方で現在はというと、このメッセージには(完全な間違いではないにしろ)否定的な見解が増えていえると思います。AIやデータはツールであり手段だからです。
しかし現実には今でも、「このデータで何かできないか?(=収益化できないか?)」という言葉を耳にします。
この言葉に従えば、素直な人ほど「データを集めて、優れたAIに投入すれば、何かが得られるのだろう」と考えてしまいます。そしてその結果、「データありき、AIありき」の手段先行のプロジェクト構造が生まれています。
AIやデータは「手段でありツール」にすぎません。これらは反復と再生産が可能なテーマに対して、拡大、高速化、自動化という手段が必要な時にはとても有効なツールですが、道具自体が価値を生むわけではないのです。
今頭にアイデアが浮かんでいるとしたら、それは断片的な発想なのか、ビジネスのロジックなのか、立ち止まって考えてみる必要があります。
発想とビジネスのロジックを区別する
「このデータで何かできないか?」という発言自体は、発想のきっかけとして悪いものでく、むしろ自然だと思います。
問題はその後で、発想がビジネスシナリオとして再構成されないことです。ビジネスのどの問題を解決する道具で、なぜその道具が価値を生むのか、というシナリオの検証が必要です。
それが欠けたまま、「このデータ・AIで業務を変える」という戦術的な目標だけが一人歩きしてするとどうなるか。
現場の担当者は、「それを達成すれば事業がうまくいくはずだ」と信じて、ビジネスの検証シナリオや仮説・ビジネスロジックに疑問を持たずにPoCに進んでしまう。
また、プロダクトアウトや根拠の乏しい模倣によって、プロジェクトの予算やゴールが設計されてしまうこともあります。
そういったプロセスが積み重なった結果、プロジェクト全体をつなぐ、論理的なビジネスシナリオが存在しない状態に陥ります。そして、さも「AIがなんとかしてくれるだろう」と考えたかのような、実行が目的化したプロジェクトが生まれてしまうのです。
発想のビジネス価値を検証し直す
AI・データプロジェクトが事業に影響を与えない、その背景にはしばしば「ビジネスシナリオが欠けている」状況が見られます。
ビジネスが成立するのは、「どんな価値を誰に提供するか/求められているか」「達成条件は何か」「どの課題を解決するのか」という一連のシナリオが存在するときです。その中のどこかで、手段として必要となった際に、AIやデータという道具が活躍します。
この順序は原則的に逆転できません。
プロジェクト構想を「特定のAI・データで何かできないか」という発想から始めるのは自然です。ただ、最終的にビジネスとして成立させるには、ユーザ価値→達成条件→課題→解決方針→手段(=AI・データ)という順に再構成し直さなければならない。
これがビジネスシナリオです。このシナリオはツリー構造のイメージで、手段やツールは枝葉、ユーザ価値やビジネスのビジョン、パーパスが幹です。ひとつの価値に対して課題や手段にはさまざまな選択の可能性があり、枝分かれしています。
AIツールやデータ活用事例などのアイデアは枝葉ですから、価値というツリーの幹からロジックが成立するか、頭の中で組み立ててみる必要があります。これがビジネスシナリオの立案です。
それが合理的なら、そのシナリオの各要素が想定通りなのかを確認していきます。これがビジネスの概念検証、いわゆるPoCです。顧客価値や事業のビジョンからスタートする、トップダウンの構成になっています。
PoCが機能不良を起こすケースでは、このビジネスロジックの組み立てに関する情報が欠けています。通常は検討されていないか、資料化されていないかのどちらかです。あったとしても抽象度が高く実務的ではなかったり(例:IR資料のイメージ図のようなもの)、ごく一部の人の頭の中だけにあったりします。
その結果、実行しやすい技術検証だけにフォーカスやリソースが集中してしまい、シナリオ全体が検証されない、という自体に陥ってしまいます。
検証不足のビジネスに対して、コンピューティングによる生産力が掛け算されると、悲劇が起こりかねません。
ビジネスの直感を信じてボトムアップで着想を得つつ、ビジネスロジックをトップダウンで整理し直す必要があります。このビジネスシナリオの整理が、PoCにおける最も重要なポイントです。
実行の目的化
PoCプロジェクトでは、「AIとデータは必ずプラスになる」「事例に対する曖昧な期待」によって、ビジネスシナリオが不透明な状態で契約が結ばれることがあります。(投資家の期待に端を発していることもあります。)
プロジェクトの承認後、担当者には目的と予算を後から覆す裁量はなく、仮に問題に気づいても軌道修正は困難です。
結果、PoCは技術実験に終始し、「やってみたが、なぜか成果が出なかった」という結末に向かいます。
この状況を回避するためには、「上流から下流までの『投資としてプロジェクトを成立させる』という論点の共有」と「開かれたコミュニケーション」が必要です。また、事業の専門性や外交に特化するマネジメント層以上には、コミュニケーションのための技術の翻訳が必要なケースもあります。
一方で、「ビジネスシナリオがないのに成功圧力がかかる」という状況は担当者にとっては理不尽です。担当者にとってのひとつの合理的な解決策は「問題点をうまく回避し、何かしらの成功を報告し、PRに辿り着き、その実績を持って離脱する」ことです。
このような表面的な成功が現実的な解決策になるケースは、おそらく珍しくないのではないか、と思います。成功圧力や失敗のペナルティ、キャリア志向が強いほど、この選択のインセンティブは上がります。
仮説と課題設定が出発点になる
データを活用した意思決定は、「結果が好ましいから採用する」(例:あからさまな相関が出た)べきではありません。
それは意思決定というよりは自動化の領分で、データを集める前から概ねわかっている必要があり(=仮説があり)、データでそれを裏付けることで実現します。データによって発見を期待していいものではありません。
では手堅いデータの活用方法は何なのかというと、「ビジネスロジックとして適切な判断に対して、データで裏付けを取る」ことです。
自動化にしろ意思決定支援にしろ、まず最初に「何を判断したいのか」「何が解決したい課題なのか」、つまり仮説を明確に言葉で書く必要があります。そしてその後、それをどう数字で表現するかを考えます。
たとえば、アイスクリームの販売を改善したいとき、「売上と気温が関係あるはずだ、なぜなら暑い日には冷たいものを食べて体を冷やしたくなるはずだからだ」と思ったなら、それが仮説です。
ではどう検証するか?例えば、気温は気象データを取り込むことで確かめられるかもしれません。
それは前日からの気温の上昇幅でしょうか。例年の平均気温との差でしょうか。それとも絶対値としての気温でしょうか。これを考えるには、「暑い日には冷たいものを食べたい」という感覚をより深く分解して解釈し、表現するにはどの数値表現が妥当かを、頭の中で分析していく必要があります。
売り上げを予測するなら絶対量が妥当でしょうか。前月比、トレンドが妥当でしょうか。そういう問いも出てくるはずです。
アイスの話はここまでにして、大切なのは、「明確な仮説があって初めて、必要なデータや表現方法が定まる」という、1. 問題定義、2. 解決手段の順序関係です。
反対に、売上データや顧客属性を闇雲に分析しても、「それで何を判断したいのか」が決まっていなければ、意味のある示唆にはなりません。データとAIはあくまで分析の手段だからです。
そのようなアプローチの現場では「あからさまな相関がなかったから意味がない」「知っている結果が出たから意味がない」という感想が出てくる可能性が高いです。
「AIとデータ」というキーワードを起点にしたアプローチと実務的なアプローチのズレがここにあります。
補足:
2025年初頭の時点ではすでに、言語モデルと分析の組み合わせによって、一般的なアプローチでの分析はかなり簡単になりつつあります。
たとえば、「こういう目的で、こういう分析をしたい」とLLMに伝えると、LLMが分析を提案し、実行まで担ってくれる。これは全自動のケースもあれば、担当者に依頼することで(担当者がLLMで分析手段を調査し)自然とそのようなプロセスになることもあります。これはすでに現実になっています。
ここで、言語モデルは分析をディレクションする手段、分析ツールが分析自体の実行手段、としてそれぞれ機能しています。データ分析という手段については、かなり合理化が進んでいるのです。
だからこそより重要になるのが、「どんなビジネス価値を裏付けるために、何の分析をしたいのか」「分析以外には何を検証すべきか」というビジネスロジック、検証シナリオ設計の部分です。
シナリオ設計に関する知見、判断力、そして柔軟性や独自性は、意思決定層やマネジメントが担うべき領域であり、むしろ以前より価値が高まっていると言えるでしょう。
投資判断にも構造的な視点が必要
目的や投資の設計でも、次のような視点が欠けているとリスクが増大します。
- 短期で測定可能な目標(例:コストの削減)なのか
- 長期的・定性的で測定が難しい価値(例:新たなサービスの開発、ブランド・ポジションの変更)なのか
この区別が曖昧なまま、「KPIやROIを明確にせよ」という判断基準だけで横並びに評価してしまうと、長期的に意味のあるプロジェクトが正しく扱われず、低リスク・低リターン・競争の激しい(測定や予測が可能で、利益にも直結するので、多くのプレイヤーが参加し、資本で優劣がつきやすい)領域に投資や戦略が集中することになりかねません。
見極めるべきは「中身のあるPoC」かどうか
現在の「AIとデータを活用する」というメッセージには、かつての期待を煽る目的というよりは、むしろ「経験の浅い潜在顧客を浮き上がらせる」ために発されている側面もあるように思います。
PoCや導入支援を外部ベンダーに依頼する場合にも、「技術実験や型式的なプロセス・インフラ導入として支援したいのか」「ビジネスの仮説検証を支援したいのか」、こちらの意図を伝えると同時に、ベンダーのビジネスの意図を見極める必要があります。
おわりに
AIやデータを活用して価値を生むには、「仮説→課題設定→方針→手段」という論理構造を組み立てる必要があります。手段から始めてしまうと、意思決定にはブレが生まれ、現場は空回りし、投資は回収されません。
「AIで何かできないか」という問いから始まっても構いません。
ただし、それをビジネスとして価値あるプロセスに変換できる構造を持たない限り、成功は偶然性に強く依存します。
それが、この分野における大きな落とし穴だと考えています。
そしてもちろん、ここに書いてあるのはあくまでも「PoCに関する実務の経験値を補うための視点」です。
ビジネスロジックの整理は当然行っていて、技術領域に閉じない検証シナリオが存在する。現場からのエスカレーションを適切に受けて目標を軌道修正できる。世の中のDXの取り組みが成熟するにつれ、そういう組織は増えました。
ある程度の「PoCの迷走による失敗経験」を下敷きにして学び、また、マネジメントの目線でAI・データプロジェクトを見直した人材や組織、あるいは意思決定層がいた/招いたからでしょう。
逆に現在のPoCにビジネスロジックがない、技術単体の検証に見える、成功の報告はあるがビジネスインパクトが不透明だ、と感じるのであれば、マネジメントの視点でPoCを見直してみることを推奨します。
LONGBOWでは、PoCやAI活用の“ビジネスロジックの欠落”に対して、仮説設計・シナリオ整理から支援するアドバイザリーサービスを提供しています。PoCを通じた価値創出に不安や課題があれば、ぜひご相談ください。